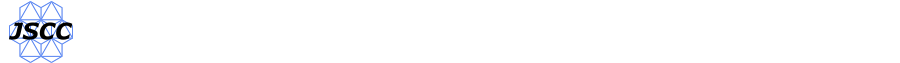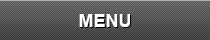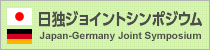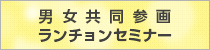シンポジウム
- The State of the Art Metal Cluster Chemistry: from Synthetic Methodology to New Functionality
- Toward an Integrated Biometal Chemistry: Emerging Approaches to Rigorous Comprehension of Biological Systems
- New Aspects in Two-dimensional Materials -Focusing on Fusion with Coordination Chemistry-
- On-demand Photofunctions in Coordination Chemistry from Mysterious Luminescence to Solar-energy Conversion
- Capture and Activation of Small Molecules in Coordination Chemistry and Bioinorganic Chemistry
- 溶液の目で見る錯体化学 ~溶液中での錯体分子の本質的な役割~
溶液の目で見る錯体化学 ~溶液中での錯体分子の本質的な役割~
開催代表者
小谷 明(金沢大医薬保)
田所 誠(東京理科大理)
佐竹 彰治(東京理科大理)
プログラム (G201:シンポジウム S6会場)
16:30-16:35
開会の辞:小谷 明 (金沢大医薬保)
第1部 <非共有結合的相互作用に基づいた錯体科学>
座長 佐竹 彰治(東京理大理)
(S6-01) 16:45-17:05(発表15分 質疑応答5分)
分子性多孔質結晶に閉じ込められた水クラスターの科学
(東京理大理)田所 誠
座長 田所 誠 (東京理大理)
(S6-02) 17:05-17:25(発表15分 質疑応答5分)
置換活性な配位結合が誘起する亜鉛ポルフィリン多量体の構造変化
(東京理大理)佐竹 彰治
(S6-03) 17:25-17:50(発表20分 質疑応答5分)
複数の相互作用を活用した配位性一次元分子集合体の構築
(名城大理工)藤田 典史
17:50-17:55 コメンテーターによる第一部の講評
17:55-18:05 PC接続
第2部 <生体・自然界に備わる錯体の特性>
座長 小谷 明(金沢大医薬保)
(S6-04) 18:05-18:30(発表20分 質疑応答5分)
青色花の発色と金属錯体化学
(名古屋大情報)吉田 久美
座長 立屋敷 哲(女子栄養大)
(S6-05) 18:30-18:55(発表20分 質疑応答5分)
生体酵素の活性部位を溶液中に取り出す錯体化学
(大阪大理)舩橋 靖博
(S6-06) 18:55-19:15(発表15分 質疑応答5分)
タンパク質と金属,薬物との結合研究から見えてきた溶液研究の魅力
(金沢大医薬保)小谷 明
19:15-19:20 コメンテーターによる第二部の講評
19:20-19:25 閉会の辞 佐竹 彰治(東京理大)
趣旨説明
本申請シンポジウムは立屋敷先生(女子栄養大)が昨年行ったシンポジウム「溶液の目で錯体化学の他の分野を見る」の 第二弾を意図した。すなわち,現在の錯体化学討論会では「溶液に関わる錯体研究者」が各会場バラバラになってしまっており、継続的 に溶液系の錯体化学者の人的交流をつくる場としてシンポジウムを継続することが必要と判断した。
しかし,本シンポジウム「溶液の目で見る錯体化学 ~溶液中での錯体分子の本質的な役割~」は溶液研究者の集まりが目的ではない。「溶液の目で見る」は,
- これから時代をささえる若い研究者に,広い目・興味で研究を展開して欲しい,既成の権威・流行の学問にだけ目・頭がとらわれないで欲しい,ユニークな研究を行って欲しい,本シンポジウムをその基礎として欲しい。
- 現役の一線の研究者にも,一度立ち止まって,今までの自分と違う目(=溶液の目)で見て,個々の研究を「深める」きっかけとすることも、「溶液の目で見る」、シンポジウムの大きな目的の一つである。
したがって,視野・興味の幅を拡げる意味で、目新しい講演、聞いたことのない講演が大変重要であり,この観点から,錯体化学討論会にはまず出席されない吉田久美先生(名大)に花の色の金属錯体を含む超分子の生成過程を,相田先生のお弟子さんの藤田典史先生(名城大学理工)にフェロセンナノチューブをフェロセンの回転パーツを持つ分子がどのようにして溶液中からチューブ状に組み上がっていくかの生成過程をお話いただき,既成の錯体化学を,別の目で見る,広い視野から批判的に見ることに挑戦したい。残りは錯体組が,それぞれ各自の批判的な目から,これまたこれまでの錯体化学に欠けていることについて講演,discussionし,聴衆にカルチャーショックを与えることを目的とする。
シンポジウムの組み立てとしては,異分野交流を念頭に,境界分野の教員にセッションのテーマに関する導入を兼ねた教科書的・初歩のトークも含めた講演の後,セッションのテーマにかかわるご専門の応用的なご研究をご紹介頂き,その後コメンテーターを中心とした討論を行う形式を取って,若い人たちに普段聞けないコメント等様々な立場からのdiscussionを聞いていただく。